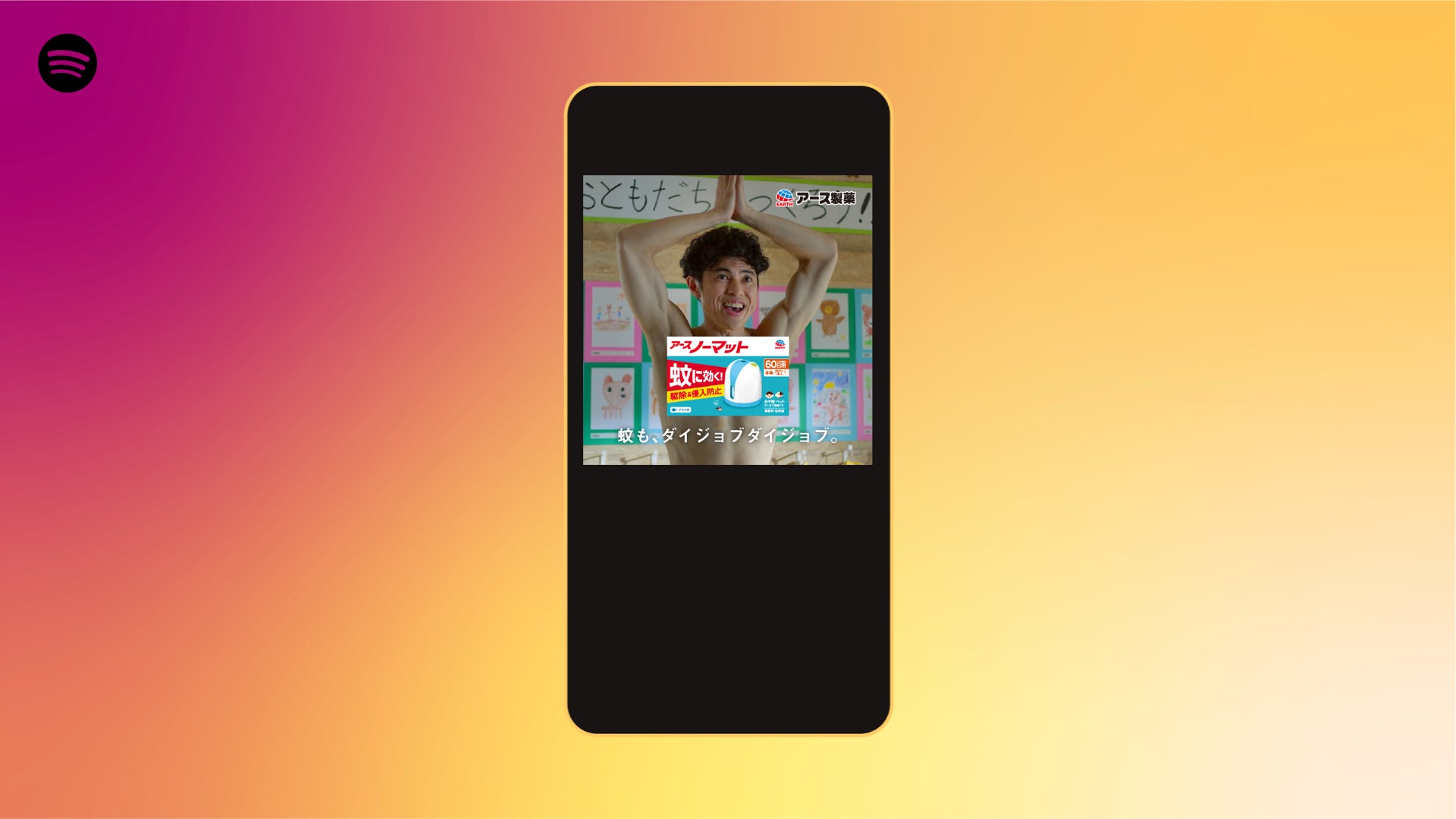Spotifyは2025年11月10日、恵比寿のBLUE NOTE PLACEにて、広告事業者および広告会社向けのイベント『Spotify Hits Japan 2025』を開催しました。

このイベントは、日本では今年で2回目となるSpotify主催の広告賞『Spotify Hits』の授賞式として開催。昨年から規模を拡大し、3つの部門賞とグランプリである「Spotify Mic Drop」に加え、公募制の「Future Hitmakers」から3作の受賞作品が発表されました。
会場には、合計100名を超える受賞者やファイナリスト、広告主・広告会社関係者が集まりました。
開会の挨拶には、この日のためにニューヨークから来日したSpotify グローバル広告事業クリエイティブ戦略統括のケイ・スー(Kay Hsu)が登壇。クリエイター、ブランド、パートナーへの心からの感謝を述べ「みなさんのクリエイティビティ、そして音の力を信じるその情熱がこの機会を特別なものにしています」と語りました。『Spotify Hits』は、革新的な音声広告を称える場として始まりましたが、いまでは「クリエイター、マーケター、ストーリーテラーたちが音の可能性を広げるために集うコミュニティ」にまで進化していると強調。特に日本市場については「本当に素晴らしい」と絶賛し「ここから生まれる作品は、大胆で感情豊かで、そしてとても人間的です」と評価しました。

Spotify入社前のHsuはビジュアルメディアでブランドのストーリーテリングを手がけていたが、音声コンテンツと出会うことで「価値観が変わった」と告白。「音には人の心を動かす不思議な力があるし、目には見えないけれども心に残る」こと、その力がSpotifyを特別なプラットフォームにしているのだと述べました。最後にHsuは「みなさんはトレンドを追う側ではなく、トレンドを作る側です」と、会場に集まったクリエイターたちを鼓舞し、「想像力を祝い、チャレンジを称える」一日になることを期待し、授賞式が幕を開けました。

ここからは、実績のあるキャンペーンを対象とした3つの部門賞とグランプリの授賞式の模様を、プレゼンターによる選考コメントと受賞者の喜びの声に焦点を当ててご紹介します。
〈Ear Candy部門(ベストイマーシブオーディオキャンペーン)〉
受賞作品:『サラウンドコマーシャル「円陣」&「円陣(部活)」』
広告主:大塚製薬(ポカリスエット)
広告会社:電通 / 電通デジタル
制作会社:ビッグフェイス / ステップ / 音響ハウス
「3DオーディオやASMR、スクリプトの工夫など、音声ならではのテクニックを活用して最も没入感のある体験を実現したキャンペーン」を表彰する部門である〈Ear Candy部門(ベストイマーシブオーディオキャンペーン)〉のプレゼンターを務めたのは北原規稚子氏(MICHI inc. CEO / Brand Creator)。

北原氏は「Spotifyユーザーの8割以上がイヤホンを使用して聴いている」というデータを踏まえ、審査では「リスナーの体験を邪魔せずに楽しんでもらえる没入感ある体験を、いかに実現できているか」 という点を重視したと説明しました。受賞作である大塚製薬株式会社(ポカリスエット)の『サラウンドコマーシャル「円陣」&「円陣(部活)」』については、ブランド体験として「シンボリックに象徴される部活の円陣のシーンに一気に連れていかれるような世界観」 が作り込まれている点を評価。「Spotifyのテクノロジーや特性、聴いているターゲットの状況をよく理解された上で作られていた」と絶賛しました。

今回の受賞について、大塚製薬の受賞者は「他メディアでは映像中心の施策が多いなか、『音だけで感情を動かす新しいアプローチ』に挑戦した」と語り、バイノーラル録音で臨場感ある音を再現し、リスナーが円陣の中にいるような感覚を楽しめるよう徹底的に音にこだわった結果、「音で汗を感じる」没入感ある広告体験を実現できたと明かしました。
〈Seized the Moment部門(ベストモーメントキャンペーン)〉
受賞作品:『家路言』
広告主:サントリー(金麦)
広告会社:電通
制作会社:AOI Pro.
「特定のモーメントを捉え、クリエイティブなアプローチでユーザーとエンゲージしたキャンペーン」 を表彰する〈Seized the Moment部門(ベストモーメントキャンペーン)〉のプレゼンターを務めたのは和佐 高志氏(Jukebox Dreams 代表取締役CEO)。

和佐氏は同部門について「Spotifyならでは、かつブランドと親和性の高いモーメントを的確に捉えている」 作品が多かったと振り返り「広告ではなく“モーメント”、重要なのはリアルタイムでありコンテンツ、という時代が来ています」 と広告の概念の変化について言及。受賞作の金麦『家路言』については、仕事帰りにオンからオフへ切り替わる「帰宅中」というモーメントの刈り取り方が「すごく妙でした」と評価。特に、電車やバスなどの「環境音」が入っており、リスナーが意識することなく「その世界に没入して自然に入っていく」 パワーが素晴らしかったと述べました。

受賞について、担当者は「従来の『帰れば金麦』というコミュニケーションに加え、これまで交通広告程度で手つかずだった『帰宅動線』をどう捉えるかをクリエイターと共に考えた」と種明かしをしてくれました。また、企画のインサイトとして、冒頭にゆったりした曲調にアレンジした「蛍の光」を流すことで「オンの状態からオフへのスイッチになった」という発見が、クリエイティブの価値を決定づけたと説明しました。結果として、ROIは約170%改善、広告認知も20〜40代で150%向上という成果を収めたと語りました。
〈For the Fans部門(ベストオーディエンスストラテジーキャンペーン)〉
受賞作品:『い・ろ・は・す 2025年コミュニケーション「きっとあしたも、いい感じ」』
広告主:日本コカ・コーラ(い・ろ・は・す)
広告会社:電通 / 電通デジタル
制作会社:VML & Ogilvy Japan / WPP OpenX / プラチナム / アクセンチュア
「Spotify上のアーティストやクリエイターのファンたちと効果的にエンゲージしたキャンペーン」 を表彰する部門である〈For the Fans部門(ベストオーディエンスストラテジーキャンペーン)〉では、Dos Monosのメンバーであり、クリエイティブディレクターとして活躍しながら、人気音声コンテンツを多数手掛けるTaiTan氏(ラッパー・クリエイティブディレクター)がプレゼンターとして登壇。

TaiTan氏はアニメ、声優、人気アーティストなど「性格が全然違う」 ファンダムを捉えた作品が並び「決め手をどこにするかで悩んだ」 と審査の難しさを語りました。その上で受賞作の『い・ろ・は・す 2025年コミュニケーション「きっとあしたも、いい感じ」』については「藤井風さんのような『大きなファンダムを持っているアーティスト』 にアプローチする際はコンフリクト(衝突)やハレーションが起こる可能性も極めて高いが、それを乗り越えていったことが決定打になった」と述べました。続けて「音声広告は『嫌われたら一瞬でおしまい』という世界のなかで”直球ど真ん中”を射抜いた」 重要なキャンペーンだと評価しました。

受賞者は「若年層との『より強い絆』 を求めてキャンペーンを始めた」と説明し、そのうえで「情報過多で疲れている若者に対して透明で邪魔にならない、気持ちいい存在として、『きっとあしたも、いい感じ』というポジティブな気持ちを提供したい」と考えたと語りました。その結果、非常にシンプルなキャンペーン設計ながら、ファンから非常に大きな反響を得ることに成功したと、喜びを語りました。
〈Spotify Mic Drop(グランプリ)〉
受賞作品:『#LoveYourMistake「Knock Turn」』
広告主:ヤマハ
広告会社:電通東日本
制作会社:ピラミッドフィルム / Massive Music
全キャンペーンの中で最も優れていた作品に贈られる〈Spotify Mic Drop(グランプリ)〉について、プレゼンターとして登壇したのはSpotify Japan 広告事業クリエイティブ戦略統括の橋本 昇平。

橋本は、グランプリ作品について「満場一致で決まりました」 とヤマハ株式会社『#LoveYourMistake「Knock Turn」』の名前を発表。歴史あるヤマハというブランドがSpotifyというプラットフォームを新しい使い方で活用し、世界共通のインサイトを捉えてグローバルに展開している素晴らしいキャンペーンだと評価しました。

受賞者は、ショパンのノクターンという有名な楽曲を崩すことは「かなりギリギリの判断」 だったと認めつつ、メッセージを貫き通したチームに感謝を述べました。企画の背景には、楽器練習に取り組む時間の「8〜9割は苦しい時間である」 というユーザーインサイトがあったと言います。「このネガティブな時間をポジティブな時間に変え、ブランドとして寄り添うこと」がメッセージだったとし、そのうえで「ただ楽曲を崩すのではなく、練習データからユーザーが「ここで間違う、ここでストップしちゃう」という箇所を抽出し、あえてそのまま楽譜に起こして制作。曲名も「ノクターン(Nocturne)」ではなく「Knock Turn」というスペルにしたと説明しました。
また、リスナーが思わずクスッと笑い、「あるある」と共感する心理設計が奏功。結果、高い聴取完了率(94.61%)と目標の約2.5倍の楽譜閲覧数を記録しました。
続いて、30歳以下の若手クリエイターを対象に実施された公募部門「Future Hitmakers(ベストイノベーティブアイディア)」 では、3社から出された課題に対し、最も優れたキャンペーンアイデアが表彰されました。
ファミリーマート賞(テーマ:フードロス削減)
受賞作品:博報堂『フード・ロス市警からのミッション “ファミマの値引き商品を救出せよ”』
審査員:足立 光氏(ファミリーマート チーフ・クリエイティブ・オフィサー)
制作会社:西村亮平 / 清水将也(いずれも博報堂)
足立氏は、トランシーバーの音から始まる「キャッチーさ」 や、「音声による行動喚起」 の観点でアイデアを高く評価。値引き商品を「助けよう」というコンセプトが、ファミリーマートの「いろんな可能性に一貫している」 と述べました。

受賞チーム代表の西村氏は、ファミリーマートの「涙目シール」という既存施策の上に、Spotifyのプラットフォームの強みを使って「体験を拡張させよう」 としたと説明。「無線通信風」のクリエイティブ表現も功を奏し、考えた世界観を「聴覚的に立体化する」 ことができた喜びが語られました。
味の素賞(テーマ:若年層向けコミュニケーション)
受賞作品:ワンメディア『猫舌クノール 〜聴き終えると、ちょうどいい温度になるプレイリスト〜』
審査員:向井 育子氏(味の素 食品事業本部マーケティングデザインセンター副センター長)
制作会社:小宮寛平(ワンメディア)
向井氏は、「ブランドイメージとのマッチングが最終的な決め手」 とし、「猫舌」という切り口が、スープを熱い温度で溶かさなければならないが故にすぐ飲めない、というインサイトを捉えており、共感を呼ぶと評価。クノールの基本価値である「心と体を温める」という優しさと合致していた点を絶賛しました。

受賞者の小宮氏は、自身の猫舌の経験から、スープが「ちょうどいい温度になるまで待てばいい」 と考え、その待ち時間をSpotifyらしく「音楽をディグする時間」 に変えることを発想の出発点としたと明かしました。
KDDI賞(テーマ:UQ mobileがつなぐ、青春の瞬間)
受賞作品:電通デジタル『一生ものプレイリスト』
審査員:馬場 剛史氏(KDDI ブランド・コミュニケーション本部 本部長)
制作会社:髙屋敷日奈子 / 大川憧子 / 植木隆斗(いずれも電通デジタル)
馬場氏は、審査は混戦だったが、受賞作は「UQ mobileらしさ」 から企画を立てており、同社の企業理念である「つなぐ」 が企画にしっかりと落とし込まれている点を評価。また、「ギガがいっぱい使える」 というUQ mobileの特徴ともコンセプトが合致していたと述べました。

受賞チーム代表の高屋敷氏は企画について「『ずっと聴いている曲って高校生や中学生時代の曲ばかりではないか?』 という気づきから、それを示す研究結果のファクトに着目した」と説明。工夫した点について、学生にとって「いま聴いている曲は一生ものになる」と訴求し、親世代にも「この子がたくさん音楽を聴けるよう、ギガの多い会社にしよう」と思わせる共感設計にしたとし、さらに、Spotifyが毎年年末に行う「Spofiryまとめ」のようなまとめ機能を活用し、10代が今年一番聴いた曲が一生もののプレイリストになるというアイデアを提案しました。

授賞式の後には、Spotifyの橋本と博報堂の嶋浩一郎氏、電通の佐藤雄介氏によるパネルディスカッションや、19歳の大学生シンガーソングライターAKASAKIさんによるスペシャルライブパフォーマンスが行われ、受賞者やファイナリストたちを祝福しました。

閉会の挨拶を務めたのは、Spotify Japan 執行役員 営業本部長の田村 千秋。「昨年初めて開催してから1年間、その間にこんなに進化すると思わなかった」 と語り「みなさんと一緒にトレンドを作れていることをすごく光栄に思っています」 と、デジタル音声広告クリエイティブの急速な進化への驚きと喜びを表明しました。
なお、授賞式終了後にはネットワーキングタイムが設けられ、来場者たちはSpotifyのロゴが入った限定フードやドリンクを楽しみながら、クリエイティビティへのインスピレーションを共有しました。
Spotify広告の「音の可能性」がどこまで広がるのか、その未来への期待が高まるばかりです。